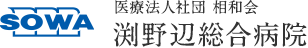| 名称 | 医療法人社団 相和会 渕野辺総合病院 |
|---|---|
| 開設 | 昭和29年8月 |
| 所在地 | 神奈川県相模原市中央区淵野辺3丁目2番8号 電話:042-754-2222(代)/ FAX:042-757-4170 |
| 病床数 | 181床 |
| 施設 | 敷地面積:4542.29m2 建築面積:3376.97m2 延床面積:15122.13m2 鉄筋コンクリート造 8階建 |
| 診療科 | 内科、小児科、外科、眼科、整形外科、脳神経外科、産婦人科、泌尿器科(尿路結石治療センター)、麻酔科、放射線科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科 |
| 休診日 | 土曜日(午後)・日曜日・祝日、年末年始(12月29日PM~1月3日) |
| 主な検査・治療機器 | マルチスライスCT/超音波診断装置/電子内視鏡装置/乳房X線撮影装置/X線テレビ装置/MR撮影装置1/超音波白内障手術装置/骨塩定量測定装置/ホルミウムYAGレーザー/体外衝撃波結石破砕装置 その他 |
保健指導機関情報
相模原総合健診センター 保健指導機関情報 をご確認下さい
|
基本診療料の施設基準
|
|
|---|---|
|
|
|
特掲診療料の施設基準
|
|
|
|
|
診療指定
|
|
|
|
<目標>
①良質な医療を継続的に提供するため、従来より推進してきた各部署間の協力体制
を医政局通知に基づき再整備し、医師、看護師等の医療専門職が専門性を必要
とする業務に専念することができるよう、各業務の分担を更に推し進める。
②目標達成に向けて、院内外等の研修に積極的に参加し各職種の能力向上に努める。
<継続的な業務分担の推進>
①医師に対して
・医師事務作業補助者の育成及び事務員の有効活用、配置について
・医師が実施している検査・入院説明および書類対応の役割分担について
・カルテ記入や書類作成等、入力方法の負担軽減を検討する
・病棟への薬剤師配置拡充および業務拡大について
②看護師に対して
・看護職と看護補助者および事務の業務分担について
・看護師が実施している検査・入院説明および書類対応の役割分担について
・病棟への薬剤師配置拡充および業務拡大について
・短時間正規雇用の看護職員の活用について
<継続的な業務分担の推進>
①医師事務作業補助業務拡張のため、院内研修を行い病棟への医師事務作業補助者配置
②外来における検査説明の診療科拡大
③薬剤師の雇用および病棟配置、業務拡大へ向けた薬剤部体制の安定化
④看護師及び看護補助者の業務内容の見直し
①良質な医療を継続的に提供するため、従来より推進してきた各部署間の協力体制
を医政局通知に基づき再整備し、医師、看護師等の医療専門職が専門性を必要
とする業務に専念することができるよう、各業務の分担を更に推し進める。
②目標達成に向けて、院内外等の研修に積極的に参加し各職種の能力向上に努める。
<継続的な業務分担の推進>
①医師に対して
・医師事務作業補助者の育成及び事務員の有効活用、配置について
・医師が実施している検査・入院説明および書類対応の役割分担について
・カルテ記入や書類作成等、入力方法の負担軽減を検討する
・病棟への薬剤師配置拡充および業務拡大について
②看護師に対して
・看護職と看護補助者および事務の業務分担について
・看護師が実施している検査・入院説明および書類対応の役割分担について
・病棟への薬剤師配置拡充および業務拡大について
・短時間正規雇用の看護職員の活用について
<継続的な業務分担の推進>
①医師事務作業補助業務拡張のため、院内研修を行い病棟への医師事務作業補助者配置
②外来における検査説明の診療科拡大
③薬剤師の雇用および病棟配置、業務拡大へ向けた薬剤部体制の安定化
④看護師及び看護補助者の業務内容の見直し
医師ならびに医療従事者の負担軽減計画
| 項目 | これまでの実施状況と評価 | 内容 | 令和7年度計画 |
|---|---|---|---|
| 労働時間管理等 | ●ICカードを用いた勤怠管理システムによる出退勤の把握により勤務時間の把握が容易になった。 ●勤怠管理システムによる年次有給休暇取得率の把握が容易になった。 ●以下の内容を実施しており負担軽減につながっている。 ・勤務予定作成時、連続当直とならないような日程調整 ・非常勤医師の積極的な採用 ・救急当番日への非常勤医師の雇用 ・平均月当たり当直回数の軽減 ●宿日直許可は令和5年2月28日付けで許可を受けている。 |
・労働時間および休暇取得状況の把握 ・当直者への負担軽減 ・宿日直許可 |
・放射線室、検査室における交代制勤務の導入 ・2次救急日における医療技術部門の交替制勤務の導入検討 |
| 多職種との業務分担 | ●診療科医師の指示のもと医師事務作業補助者が各種オーダーについて代行入力を行っている。 ●生命保険用診断書作成、患者受診報告書作成、症例登録などの事務作業を事務職で行っている。 ●医師や看護師が行っていた検査や手術の説明を事務職で行っている。 |
・オーダー入力代行 ・医師の事務作業軽減 ・検査説明、手術説明 |
・代行業務の拡大 |
| 職員の勤務環境改善 | ●外国人技能実習生を受入れ、入浴介助、食事配膳、検査付き添いなど看護補助者の業務を補助。 | ・技能実習生受入れ ・病院利用者から受ける、言動、暴力、セクハラ等への対応 ・更衣室等の見直し ・DXによる業務効率化 |
・医療法人社団相和会におけるカスタマー・ペイシェントハラスメント対応姿勢の策定 ・別棟にある更衣室を病院と同一建物内に設ける ・更衣室付近に職員用車イス対応トイレを設ける ・職員用休憩室の増設 ・AIによる議事録作成 |
| 多様な勤務形態・子育て介護支援 | ●24h対応の院内保育所を設置しており、いつでもお子さんを預けられる体制を整えている。 ●定年退職者の嘱託雇用規程を定め、希望者は65歳まで勤務ができるようになり、技術継承等につながっている。 |
・出産、子育て、介護中の職員への配慮 ・定年退職者の雇用継続 |
・育児・介護休業法の改正への対応 |
看護師負担軽減計画
| 項目 | 令和6年度実施状況と評価 | 令和7年度計画 |
|---|---|---|
| 他職種との業務分担 | 〇服薬指導の件数が増えてきている。病棟薬剤師が配置されており病棟内の安全な薬剤管理について引き続き依頼していきたい。 〇病棟での朝の採血については実現しなかった。外来の検体運搬に関して協力をいただき負担軽減につながった。 〇MEにより、エアマットやネブライザーなどの看護用具の管理がおこなわれるようになっている。次年度も継続的に進めていきたい。 〇病棟物品のSPD化の検討と共に、物品請求業務の効率化・負担軽減は実施でききなかった。 〇リハ職員によるリハビリ患者送迎の継続・リハビリ補助者によるシーツ交換の継続。 〇検査時の介入 ・検査時の問診及び同意書の受領、IVライン抜針 〇病棟クラーク、外来事務の業務改善と役割分担としたが、改善はすすまなかった。外来患者の増加というだけでなく高齢者が多く、事務も看護も余裕がない状況。診療から会計までの流れを整理し負担軽減を図っていく必要がある。 〇現在、配茶方法の検討、コップ・箸・スプーンの洗浄と配布に関して検討中大きな負担軽減と患者の安全な療養環境につながる取り組みになる。 〇診療情報管理室による検査説明MRI,胃カメラの説明を実施している。CFの説明についてはまだ行われていない。 |
〇薬剤部:病棟内の安全な薬剤管理 薬保管庫の正式名称での表記 〇放射線科:検査時の点滴挿入及び抜針 点滴抜針から開始の計画があり、引き続き点滴挿入迄拡大 〇栄養部:コップ・箸・スプーンの洗浄 |
| 看護職員の勤務環境改善 | 〇看護師の確保 ・今年度は看護専門学校4校に加え、看護大学3校を訪問。採用に向け当院が求める看護師について話をさせていただく。看護専門学校実習受け入れ2校、インターンシップ22名、1日看護体験14名、介護福祉課の学生1日介護体験3名の受け入れ。看護師募集サイト等確保に取り組んだが、非常に難しい現状。 ・新人看護師の離職はなく看護師・看護補助者の定着にむけて働く環境の整備にも取り組んだ。 〇看護師の育成 ・看護師の育成に関しラダー教育の実施。概念化教育は2年半教育サポーターの支援を受けながら行った。今後は新たな形で概念化教育を継続するとともに、ラダー教育プログラムの内容をブラッシュアップさせ取り組んでいく必要がある。 〇メンタルサポート ・9月に新人全員の面接を実施。 ・メンタルサポートが必要な職員に関して、精神科医の面接を活用 〇ヘルシーワークプレイス ・勤務時間外労働の削減に向けて、業務の見直し、重複業務の削減を実施。申し送りの見直しや部署の状況に合わせた看護方式の検討・実施した。 |
〇看護師の確保 〇看護師の育成 ・看護師の希望を取り入れたうえで、院内ローテーションや院内留学などの仕組みを構築し、実施に向けて取り組む。 ・院内教育に院外講師を招くなど内容をブラッシュアップする。 〇メンタルサポート メンタルサポートが必要な職員に関して、精神科医の面接を活用 〇ヘルシーワークプレイス 業務内容を検討し、仕事前残業の削減。現状を把握したうえで時間外勤務の削減を目指す。 |
| 看護補助者の活用 | 〇護補助者の確保 ・看護補助者の採用に関して、ハローワークのほかタウン誌に求人広告を掲載し、勤務形態も柔軟に対応している。介護福祉課の学生を対象に体験も行った。 ・タイからの技能実習生は今年度から2名となったが、2名とも積極的に学んでおり、指導者の熱心な指導により定期試験も合格し、継続して就業できている。 〇看護補助者との協働 ・看護師長・主任看護師等に対する「看護補助者との協働のための研修」に管理者3名受講。看護補助者との協働に必要な教育を管理職、全看護職員、看護補助者、を対象に院外研修・院内及びeラーニングにて受講するプログラムを今年度も実施。マニュアルの整備も実施した。 〇介護福祉士及び看護補助者の教育体制整備 ・介護福祉士が中心となり介護福祉士ラダー及び教育計画、教育委員会が看護助手のラダー及び教育計画の作成。次年度から使用開始予定 |
〇看護補助者の確保・定着 〇介護福祉士及び看護補助者の育成 介護福祉士及び看護補助者ラダーを活用し、現状を評価。レベルに合わせた教育の推進 |
| 多様な勤務形態・子育て介護支援 | 〇育児休暇明けの配置部署や短時間勤務に関して、本人の希望を取り入れている。 〇短時間勤務の非常勤看護師も採用し、部署での役割を果たしている。 〇時間有給の導入はできなかったが現在多彩な勤務体系で対応できている。 〇介護時短の活用や、勤務調整などにより働き続けられる環境を整えている。 |
〇育休明けの配置・時短勤務希望を取り入れ、仕事の継続ができるようサポート 〇介護が必要なスタッフの勤務希望を取り入れ、仕事の継続ができるようサポート |
1.趣旨
人生の最終段階における治療の開始・不開始及び中止等の医療のあり方の問題は、従来から医療現場で重要な課題となっている。厚生労働省においても、人生の最終段階における医療のあり方 について、平成 19 年にガイドラインが策定され、平成 30 年には、近年の高齢多死社会の進行に伴う在宅や施設における療養や看取りの需要の増大、地域包括ケアシステムの構築、アドバンス・ケア・プランニング(Advanced care planning: ACP)の概念を盛り込み、医療・介護の現場における普及を図る目的で改訂されている。
渕野辺総合病院においても、がん患者や高齢者、身寄りのない方が増加し、人生の最終段階での医療の選択・決定をする場面がたびたび発生している。そこで、厚生労働省の「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」を基に医療・ケアチームが適切な情報提供と説明に基づいて本人が医療・ケアの方針を決定することを支援するための指針を定める。
2.目的
この指針は、本人・家族等と医療・ケアチームが最善の医療・ケアを作り上げていくため本人の意思決定が尊重されることを基本として、医療・ケアを進めることを目的とする。
3.意思決定プロセスにおける医療・ケアの方針の決定手続き
(厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」より抜粋)
⑴ 本人の意思が確認できる場合
① 方針の決定は、本人の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされることが必要である。
そのうえで、本人と医療・ケアチームとの合意形成に向けた十分な話合いを踏まえた本人による意思決定を基本とし、多専門職種から構成される医療・ケアチームとして方針の決定を行う。
② 時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて本人の意思が変化しうるものであることから、医療・ケアチームにより、適切な情報の提供と説明がなされ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えることができるような支援が行われることが必要である。この際、本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等も含めて話し合いが繰り返し行われることも必要である。
③ このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、患者カルテに記載する。
⑵ 本人の意思の確認ができない場合
本人の意思確認が出来ない場合には、次のような手順により、医療・ケアチームの中で慎重な判断を行う必要がある。
① 家族等が本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。
② 家族等が本人の意思を推定できない場合には、本人にとって何が最善であるかについて、本人に代わる者として家族等と十分に話し合い、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、このプロセスを繰り返し行う。
③ 家族等がいない場合及び家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。
④ このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、患者カルテに記載する。
⑶ 複数の専門家からなる話し合いの場の設置
上記(1)及び(2)の方針の決定に際し、
・医療・ケアチームの中だけでは、患者の心身の状態等から医療・ケアの内容の決定が困難と判断した場合
・本人と医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合
・家族等の中で意見がまとまらない場合や、医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合等については、複数の専門家からなる話し合いの場を別途設置し、医療・ケアチーム以外の者を加えて、方針等についての検討及び助言を行うことが必要である。
4.「医療法人社団相和会倫理委員会」の開催については、医療法人社団相和会倫理委員会規定に準ずる。
作成 2020年8月13日
人生の最終段階における治療の開始・不開始及び中止等の医療のあり方の問題は、従来から医療現場で重要な課題となっている。厚生労働省においても、人生の最終段階における医療のあり方 について、平成 19 年にガイドラインが策定され、平成 30 年には、近年の高齢多死社会の進行に伴う在宅や施設における療養や看取りの需要の増大、地域包括ケアシステムの構築、アドバンス・ケア・プランニング(Advanced care planning: ACP)の概念を盛り込み、医療・介護の現場における普及を図る目的で改訂されている。
渕野辺総合病院においても、がん患者や高齢者、身寄りのない方が増加し、人生の最終段階での医療の選択・決定をする場面がたびたび発生している。そこで、厚生労働省の「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」を基に医療・ケアチームが適切な情報提供と説明に基づいて本人が医療・ケアの方針を決定することを支援するための指針を定める。
2.目的
この指針は、本人・家族等と医療・ケアチームが最善の医療・ケアを作り上げていくため本人の意思決定が尊重されることを基本として、医療・ケアを進めることを目的とする。
3.意思決定プロセスにおける医療・ケアの方針の決定手続き
(厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」より抜粋)
⑴ 本人の意思が確認できる場合
① 方針の決定は、本人の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされることが必要である。
そのうえで、本人と医療・ケアチームとの合意形成に向けた十分な話合いを踏まえた本人による意思決定を基本とし、多専門職種から構成される医療・ケアチームとして方針の決定を行う。
② 時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて本人の意思が変化しうるものであることから、医療・ケアチームにより、適切な情報の提供と説明がなされ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えることができるような支援が行われることが必要である。この際、本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等も含めて話し合いが繰り返し行われることも必要である。
③ このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、患者カルテに記載する。
⑵ 本人の意思の確認ができない場合
本人の意思確認が出来ない場合には、次のような手順により、医療・ケアチームの中で慎重な判断を行う必要がある。
① 家族等が本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。
② 家族等が本人の意思を推定できない場合には、本人にとって何が最善であるかについて、本人に代わる者として家族等と十分に話し合い、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、このプロセスを繰り返し行う。
③ 家族等がいない場合及び家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。
④ このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、患者カルテに記載する。
⑶ 複数の専門家からなる話し合いの場の設置
上記(1)及び(2)の方針の決定に際し、
・医療・ケアチームの中だけでは、患者の心身の状態等から医療・ケアの内容の決定が困難と判断した場合
・本人と医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合
・家族等の中で意見がまとまらない場合や、医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合等については、複数の専門家からなる話し合いの場を別途設置し、医療・ケアチーム以外の者を加えて、方針等についての検討及び助言を行うことが必要である。
4.「医療法人社団相和会倫理委員会」の開催については、医療法人社団相和会倫理委員会規定に準ずる。
作成 2020年8月13日