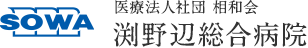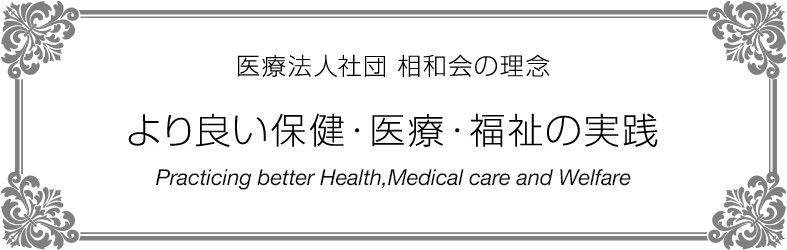

- 近隣の医療・福祉施設と共に支え合い、地域社会の人びとの健康と幸せに貢献する。
- 患者さんの自己決定権を尊重し、人間味ある温かな医療を実践する。
- 安全で良質な専門性の高い医療を提供する。
- 個人として常にその人格が尊重され、プライバシーは保護されます。
- 良質な医療を平等に受けることができます。
- ご自身の病気や治療について、充分な説明を受けることができます。
- ご自身が受ける医療を自ら選択するあるいは拒否すること、また主治医以外の意見(セカンドオピニオン)を聞くことができます。
- ご自身が受けている医療について質問することができ、必要な医療情報を得ることができます。
当院では、より多くの患者さんが適切な医療を受けられるように努めております。
そのため以下の事項につき、ご理解をお願いいたします。
そのため以下の事項につき、ご理解をお願いいたします。
- ご自身の健康や病気に関する正しい情報を提供してください。
- ご自身の治療に関して希望すること、または希望しないことを担当の医師にお話しください。
- ご自身の病気や治療について、分からないことがあれば遠慮なくお聞きください。
- 他の患者さんの療養に支障を与えないようにご配慮ください。
- 病院では、通常の社会生活にはない制約を受ける場合があります。
【職業倫理指針】
渕野辺総合病院に勤務する全職員は、ジュネーブ宣言、患者の権利に関するリスボン宣言をもとに作成された本倫理指針に基づき、責任をもって行動します
渕野辺総合病院に勤務する全職員は、ジュネーブ宣言、患者の権利に関するリスボン宣言をもとに作成された本倫理指針に基づき、責任をもって行動します
- 人間の生命・尊厳・権利を尊重し、平等な、かつ最良の医療を提供するよう努力します
- 説明と同意に基づいた患者の皆様の自己決定権を尊重し、協力のもとに医療を行います
- 多職種の良好な協力関係をもとに安全・良質なチーム医療を実践します
- 医療の公共性を意識し、関係法令を遵守します
- 患者の皆様の個人情報の保護と職務上の守秘義務を遵守します
【臨床における倫理方針】
- 患者の皆様の自己決定権を尊重し、充分な説明と同意のもとに医療を行います。
- 関係法規を遵守し、ガイドラインを尊重した医療を行います。
- 患者の皆様のプライバシーを尊重し、守秘義務を終生遵守します。
- 医療安全を最優先にして医療を行います。
- 医療に関係する多職種間の情報共有につとめ、各職種の専門性を尊重したチーム医療をおこないます。
- 生命の尊厳に関する問題、医療行為の妥当性、臨床研究に関する問題に関しては臨床倫理部会、倫理委員会にはかり、治療方針を決定します。
1.意識不明・自己判断不能の患者のための意思決定について
- 家族等が患者本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、患者本人にとっての最善の方針を考慮します。
- 家族等が患者本人の意思を推定できない場合には、何が最善であるかについて、患者本人に代わる者として家族等と十分に話し合い、患者本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、このプロセスを繰り返すことを旨とします。
- 家族等がいない場合及び家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、患者本人にとっての最善の方針をとることを基本とします。
- このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、患者カルテに記載します。
- 上記1)及び2)の方針の決定に際し、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合等については、複数の専門家からなる話し合いの場を別途設置し、医療・ケアチーム以外の者を加えて、方針等についての検討及び助言を行。
*基本マニュアル7.渕野辺総合病院における意思決定プロセスに関する指針に準じて対応する。また、身寄りのない人の手術同意書等取り扱いは基本規程集のインフォームドコンセントに準じて対応します。
2.蘇生不要指示(DNR指示)について
心肺蘇生術(CPR)の有効性について、終末期・老衰・救命不能な患者さんまたは意識回復が見込めない場合、患者さんやその家族に対して十分な説明をしたうえで、心肺蘇生術を行わない意思を示された場合は、その意思を尊重します。
3.輸血拒否について
基本マニュアル8.輸血拒否患者対応ガイドラインに準じて対応します。
4.終末期医療について
基本マニュアル7.渕野辺総合病院における意思決定プロセスに関する指針に準じて対応します。
5.検査・治療・入退院の拒否、指示不履行等について
患者さんが自律的に判断できる場合、自己決定権を尊重し、望まない治療を拒否することは認めますが、治療による患者さんの利益と不利益などを十分に説明します。
医療者と患者さんの意向が対立する場合には、臨床倫理部会において検討を依頼します。
医療者と患者さんの意向が対立する場合には、臨床倫理部会において検討を依頼します。
6.身体拘束について
身体拘束は人間としての尊厳を損なう危険性を有すると同時に身体的・精神的・社会的弊害をもたらします。身体拘束の必要性があると判断された場合であっても、身体拘束以外の緩やかな手段が考えられればそれを選択するように努めます。また、緊急時やむをえない場合の対応は、以下の3つの条件を満たすことを確認します。
- 切迫性:想定外に患者さん本人または他の患者さん等の生命や身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
- 非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと
- 身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
医療安全マニュアル「安全確保の手順」3.安全な手技の実施手順の2)身体拘束・行動制限に関する基準に準じて対応します。
7.虐待について
小児、配偶者・パートナーからのDV、高齢者の虐待を疑った場合は、基本マニュアル24.小児の虐待を疑った場合の対応、25.配偶者、パートナーからのDV被害者への対応、26.高齢者の虐待を疑った場合の対応に準じて対応します。
8.その他
その他の臨床倫理的な課題については、臨床倫理部会に於いて検討する。
2024年10月2日
2024年10月2日
倫理委員会 承認